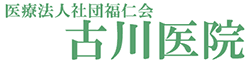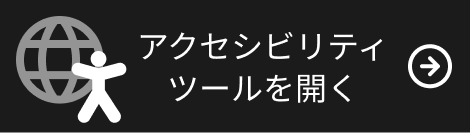RSウイルス感染症
- HOME
- RSウイルス感染症
RSウイルス感染症の特徴
RSウイルス感染症は、特に乳幼児において、重い呼吸器疾患を引き起こすことがあるウイルス感染症です。
- 潜伏期間:4~5日
- 初期症状:鼻水、咳、発熱などの上気道炎症状(かぜの症状と似ています)。
- 重症化のサイン(特に乳幼児)
- 細気管支炎や肺炎へ進展することがあります。
- 喘鳴(ぜんめい):「ヒュー、ヒュー」「ゼー、ゼー」という呼吸時の音。
- 呼吸困難や呼吸の速さの増加。
- 陥没呼吸:息を吸う時に、肋骨の間や胸の下がペコペコとへこむ。
- 顔色や唇の色が悪い(チアノーゼ)。
- 水分が取れない、哺乳ができない。
- 不機嫌、ぐったりしている(活力の低下)。
- 初回感染では症状が重くなりやすく、生後1歳未満の乳児や、早産児、心臓や肺に基礎疾患を持つ小児などは重症化しやすいハイリスク群とされています。2回目以降の感染では、多くの場合、初回感染と比較して軽症で済みます。
診断
診断は、主に臨床症状と検査によって行われます。
1.臨床診断
特徴的な症状(特に喘鳴や呼吸困難)と流行状況から総合的に判断されます。
2.検査(抗原検査)
鼻の奥などのぬぐい液や吸引液を用いて行われます。
短時間(5〜10分程度)で結果が出ますが、現在は保険診療の対象となる年齢や条件が定められています(例:外来では原則として1歳未満など)。
3.その他の検査
重症例や診断が難しい場合に胸部X線検査などが行われることがあります。
治療内容
現在、RSウイルス感染症に対する特効薬や抗ウイルス薬は確立されていません。基本的には症状を和らげるための「対症療法」が中心となります。
軽症の場合(自宅でのケア)
- 安静にし、十分な水分補給を心がけます。
- 発熱に対しては解熱剤(アセトアミノフェンなど)を使用します。
- 鼻水や鼻づまりがひどい場合は鼻汁の吸引を行います。
- 部屋の湿度を保ちます。
重症の場合(入院治療)
- 呼吸状態が悪化した場合や脱水が改善しない場合は入院が必要です。
- 酸素投与:息苦しさや酸素飽和度低下に対して行われます。
- 輸液(点滴):水分摂取不足や脱水に対して行われます。
- 呼吸管理:重度の呼吸困難に対して人工呼吸器が使用されることもあります。
- 予防薬(モノクローナル抗体製剤)
RSウイルスによる重篤な下気道炎の発症を抑制する目的で、特定のハイリスクの乳幼児(早産児、先天性心疾患、慢性肺疾患など)に対して、流行期に定期的に投与される「パリビズマブ(商品名シナジスなど)」という予防薬があります。