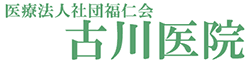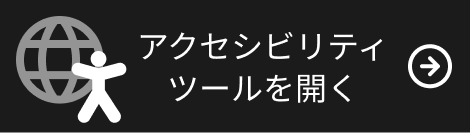- HOME
- 肛門周囲膿瘍
肛門周囲膿瘍について
小児の肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)は「乳児痔瘻(にゅうじじろう)」とも呼ばれ、大人の痔瘻とは性質が異なります。当院ではご相談があれば近隣の小児外科に紹介させていただいております。
肛門周囲膿瘍の特徴
好発時期・年齢
生後1カ月から1歳くらいまでの乳幼児に多く見られます。
性別
男の子に9割以上と多く見られます。
症状
- 肛門の周り(特に両横の3時・9時の位置)が赤く腫れて、しこりのようになる。
- 触ると痛がって機嫌が悪くなることがあります。
- 進行すると、腫れた部分から黄色い膿が出てくる(排膿・自壊)。膿が出ると腫れは一旦治まります。
- 下痢や軟便が続いた後に発症・悪化しやすいです。
- 膿がたまる→排出→治まる、を繰り返します。
原因
肛門の奥にある粘液を分泌する肛門腺に、便中の細菌が入り込んで感染・化膿することで起こると考えられています。乳児期の未熟な免疫機能も関連していると言われます。
治療内容
ご家庭での対策方法
清潔保持
おむつをこまめに交換し、排便後はぬるま湯などで肛門周囲を丁寧に洗って清潔に保つことが非常に重要です。
排膿の促進
膿が溜まって腫れている場合は、可能であればやさしく圧迫して膿の排出を促します。膿は出た方が良いとされています。
生活環境の見直し
便性を整える(下痢や便秘を防ぐ)ために、離乳食の調整や水分摂取などを考慮します。
医療機関での治療法
切開排膿
腫れや痛みが強い場合、外来で針などで小さく切開し、溜まった膿を出す処置(排膿処置)を行うことがあります。一度で出し切れない場合は繰り返すことがあります。
内服薬
漢方薬
鎮痛・排膿作用のある排膿散及湯(はいのうさんきゅうとう)や、再発予防のために腸の免疫強化作用のある十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)などが使われることがあります。
整腸剤
便性を整えるために処方されます。
抗生剤
必ずしも重要ではないとされ、使用しないことも多いですが、症状に応じて内服や軟膏が使われる場合もあります。
手術
乳児期(1~2歳まで)は自然に治ることを待つことが多いですが、2歳以降も頻繁に再発を繰り返す場合や、痔瘻が残ってしまった場合、また女の子で特殊な場所にできた場合は、手術が必要となることがあります。
最後に
肛門周囲の腫れや膿を見つけた場合は、自己判断せず、小児科や小児外科、または肛門科などの医療機関を早めに受診し、患者様にあわせた診断と治療方針を確認してください。治療には数カ月かかることもありますが、根気強く続けることが大切です。