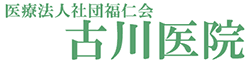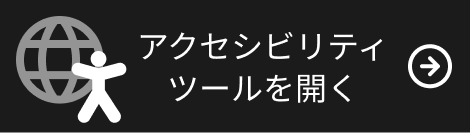- HOME
- クループ症候群
クループ症候群について
クループ症候群は、主にウイルス感染によって喉頭(声を出す部分)や気管に炎症が起こり、気道が狭くなることで特徴的な症状を呈する疾患の総称で、特に乳幼児に多くみられます。
クループ症候群の特徴
クループ症候群の3大症状は以下の通りです
- 犬吠様咳嗽(けんぱいようがいそう)
オットセイの鳴き声や犬の吠えるような「ケンケン」といった金属音のような乾いた咳。夜間に悪化しやすいのが特徴です。 - 吸気性喘鳴(きゅうきせいぜんめい)
息を吸うときに「ヒューヒュー」「キューキュー」といった高い呼吸音が聞こえる(気道が狭くなっているために起こる)。 - 嗄声(させい)
声がかすれる、または出にくくなる。
これらに先行して、数日前から微熱や鼻水など風邪に似た症状が見られることが多いです。
重症化すると、呼吸時に鎖骨や肋骨の間、みぞおちがへこむ陥没呼吸や、顔色・唇の色が悪くなるチアノーゼなどの呼吸困難のサインが現れるため、注意が必要です。
診断
1.病歴と診察
特徴的な咳(犬吠様咳嗽)、嗄声、吸気性喘鳴の有無を確認します。特に呼吸の状態(吸気の苦しさ、陥没呼吸の有無、呼吸音)や声のかすれ具合が重要視されます。
2.重症度評価
症状の程度に応じて、クループスコアなどを用いて重症度を評価し、治療方針を決定します。
3.画像検査
診断を支持するためや、他の重症な疾患(急性喉頭蓋炎など)との鑑別、肺炎の合併を調べるために、頸部X線写真を撮影することがあります。クループ症候群では、喉頭の下の気道が狭くなっている像(ペンシルサインやスティーブルサイン)が見られることがあります。
4.酸素飽和度測定
血液中の酸素の量を測り、呼吸状態の評価に役立てます。
治療内容
治療の目的は、炎症によって腫れた喉や気道の腫れを抑え、気道を確保して呼吸を楽にすることです。
軽症の場合
- 安静と加湿
興奮すると症状が悪化しやすいため、安静を保ちます。乾燥した空気は刺激になるため、加湿器などで部屋の湿度を50〜60%に保ち、喉の乾燥を防ぎます。
水分補給: 咳による脱水を防ぐため、少量ずつこまめに水分を補給します。
対症療法: 発熱や咳を和らげる薬を服用することがあります(原因がウイルスなので抗菌薬は不要です)。
中等症〜重症の場合
症状が強い場合や呼吸困難を伴う場合は、病院での治療が必要です。
- 薬物の吸入
- ラセミ体アドレナリン(ボスミン):薬剤を霧状にして吸入することで、腫れた喉頭の粘膜の血管を収縮させ、気道の腫れを急速に軽減させます。効果は短時間で現れますが、持続時間は短いことがあります。
- ステロイド薬
- 内服または点滴:ベタメタゾン(リンデロン)などのステロイド薬は、気道の炎症を抑えて腫れをひかせる効果があり、吸入薬と併用することで効果の持続を期待できます。
- 酸素投与:呼吸困難が強い場合や酸素飽和度が低い場合は、酸素を投与します。
- 入院:呼吸困難などで症状が重い場合や、治療に反応が悪い場合は、入院して集中的な治療や観察が必要となります。ごくまれに、気道の狭窄がひどく生命に関わる状態となった場合には、気管内挿管が必要になることもあります。
再受診の目安
呼吸が苦しそう、唇の色が悪い(チアノーゼ)、ぐったりしている、水を飲み込めないなどの重症なサインが見られた場合は、すぐに医療機関を受診してください。夜間に症状が悪化しやすい傾向があるため、特に注意が必要です。